低用量ピル

低用量ピルとは
経口避妊薬のこと
ピルとは卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)という2種類の女性ホルモンを配合させた経口避妊薬です。またOCともいいますが、これはOral Contraceptiveの略で同じく経口避妊薬のことです。女性が主体的に使用できる、計画的な避妊を目的とした錠剤になります。
ピルは卵胞ホルモンの含有量によって大きく、超低用量ピル・低用量ピル・中用量ピル・アフターピルに分けられますが、一般的に「ピル」といわれているものは低用量ピルを指す場合が多いです。
なぜピルで避妊できるの?
女性の生理の周期は卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)で調節されています。さらに脳から分泌されるFSHとLHというホルモンがあり、これらのホルモンによりエストロゲンとプロゲステロンが調整されて、排卵や月経がおきます。本来は卵巣から分泌されるはずのエストロゲンとプロゲステロンですが、低用量ピルを飲むことで、卵巣からホルモンが出ているのでは?と脳が勘違いすることにより、脳からFSHとLHの分泌が抑制されることにより避妊効果を得ることができます。
高い避妊効果をもたらす3つの作用
・排卵を抑制する(主な効果)
・子宮内膜を変化させて受精卵の着床を妨げる
・子宮頸管の粘液を変化させて精子の子宮への進入を妨げる
低用量ピルを毎日服用することで女性ホルモンをコントロールでき、これらの作用により高い避妊効果を示します。
正しい服用で99%以上の避妊効果
低用量ピルを正しく服用した場合の避妊率はわずか99.7%と報告されています。これは他の避妊方法と比較して非常に優れた避妊効果をもつお薬なのです。

低用量ピルの効用・効果
避妊だけではありません
低用量ピルには避妊効果のほかに様々な副効用があります。
☆生理痛の軽減
☆子宮内膜症の進行抑制と症状改善
☆過多月経の改善
☆貧血の改善
☆月経不順の改善・ホルモンバランスの改善
☆排卵痛および出血性黄体のう胞化の予防
☆月経前緊張症の改善
☆プレ更年期症状の改善
☆骨粗しょう症の予防・ニキビの改善
☆子宮体癌・卵巣癌・大腸癌の予防
☆月経時期の調整
など
これらの副効用を利用して、生理に関わる様々な症状を改善することができます。
低用量ピルの種類
ピルの分類
低用量ピルの分類は複数あるため、複雑でわかりにくいですが、下記の4つの項目で分類することができます。詳しく解説していきたいと思います。
1. 自費か保険対応かの分類
2. 超低用量、低用量、中用量:含まれるエストロゲン量による分類
3. 第一世代、第二世代、第三世代、第四世代:登場した世代別の分類(プロゲステロンの量による)
4. 含まれるホルモン量が変化する相性による分類
1. 自費か保険適応かの分類
低用量ピルは元々避妊の薬として開発されました。この避妊効果を目的とする場合は自費のピルを用います。一方、月経困難症※1や内膜症※2の治療の場合には保険適応のピルを用いることができます。保険適応の薬は基本的に医療機関での診察を施行した上で処方されます。
※1月経困難症とは
月経困難症とは、月経に関わる様々な困った症状があらわれることの総称です。この月経困難症状には、月経痛、過多月経、頭痛、吐き気、腹痛、イライラ、精神的な落ち込みなど様々な症状が含まれます。広義では月経前緊張症※3や月経前不快気分障害※4なども含みます。
※2子宮内膜症とは
子宮の内側には内膜という部分があり、この内膜が厚くなることにより、妊娠に最適な環境が作られます。子宮の内膜は生理の周期の前半でだんだん厚くなり、ふかふかのベッドのような状態を作りだし、受精卵が子宮の内側に到達(着床)しやすくします。この内膜は妊娠しなかった場合には剥がれ落ちて子宮の外に排出されます。これが生理であり、医学的には月経と呼ばれます。この子宮内膜が本来あるべき子宮の内側ではないところにできる病気の総称を子宮内膜症と呼びます。子宮の表面、卵巣、腟、腸、そのほかの臓器にできることがあります。症状には月経困難症状に加えて、排便時痛や性交時痛などがあります。
2. 超低用量、低用量、中用量などのエストロゲンの含まれる量による分類
低用量ピルは配合される黄体ホルモンの種類により開発された順番で4つの世代に分類されます。開発された世代により分類されていますので第一世代が古く、第四世代が新しいということになります。スマートフォンのように新しい世代の方が性能が良いと想像されるかもしれませんが、薬に関しては新しければ良いということでもありません。 古いものにもそれぞれ良い点もあり、また今まで使用されてきた期間が長いために安心とも考えられます。
それぞれの世代に含まれる黄体ホルモンは以下になります。
・第一世代…ノルエチステロン
・第二世代…レボノルゲストレル
・第三世代…デソゲストレル
・第四世代…ドロスピレノン(超低用量ピル)
卵胞ホルモンはどの世代でもすべて同じエチニルエストラジオールが含まれています。
相性の分類
低用量ピルは、1シート内の錠剤に配合される卵胞ホルモンと黄体ホルモンの量により分類されます。
1相性
1シート内の錠剤に配合されるホルモンの量がすべて同じです。
3相性
1シート内の錠剤に配合されるホルモンの量が3段階に分かれます。
3相性の方が自身で分泌されるホルモン状態に近いと考えられています。よって副作用などが出にくい、また安定しやすいという特徴があります。一方、1相性のピルはホルモンが含まれている量が変わらないので、より変化が少なく、生理移動などの時には安定しやすいなどの利点があります。
1シートの錠剤数の違い
低用量ピルは1シート内の錠剤数により2種類に分類されます。
21錠タイプ
1シート内に実薬が21錠のみで、7日間の休薬期間があります。
28錠タイプ
1シート内に実薬が21錠とホルモンの含まれないプラセボ錠が7錠あります。
休薬期間が無いことから、飲み忘れを予防するために、毎日服用する習慣をつけることができます。
低用量ピルの服用方法
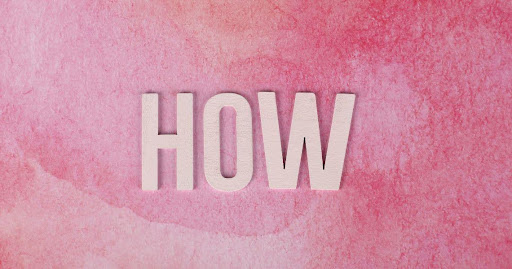
21錠タイプの場合
1日1錠を順に21日間服用し、21錠すべて飲み終わったら7日間休薬します。21錠目を服用してから2~4日後に月経のような消退出血があります。7日間の休薬が終わった翌日より新しいシートの内服を始めます。消退出血が終わっていても、続いていても新しいシートを飲み始めてください。
28錠タイプの場合
1日1錠を順に28日間服用します。最後の7錠はホルモンを含まないプラセボ錠です。プラセボ錠を服用している間に月経のような消退出血があります。28錠すべて飲み終わった翌日から続けて新しいシートを同様に飲み始めます。消退出血が終わっていても、続いていても新しいシートの服用を始めてください。
ピルによって異なる飲み始めのタイミング
Day1スタート
初めて服用する場合、通常月経の初日から飲み始めます。
Sundayスタート
月経が始まった最初の日曜日から飲み始める方法です。週末に消退出血を避けることができます。最初の日曜日が月経の初日とは異なる場合は、飲み始めの最初の7日間は他の避妊法を併用する必要があります。
飲み忘れないことが大切
低用量ピルは1日1回1錠を、毎日ほぼ一定の時間に服用することで高い避妊効果を発揮します。毎日の習慣に合わせて服用することで、飲み忘れを防ぐことができます。
・朝起きたらすぐ飲む
・朝・昼・夕食後のいずれかに飲む
・就寝前に飲む
・アラームを活用する
・目につきやすい場所に置いておく
など
服用の時間は一定であれば何時でも問題ありません。生活に合わせて、できるだけ服用時間を一定にできるよう工夫しましょう。
飲み忘れてしまった場合
1日分飲み忘れた場合
気が付いた時点で飲み忘れた1錠を直ちに服用し、その後は通常通りに服用します。つまりその日は合計2錠服用することになります。
2日以上連続して飲み忘れた場合
服用を中止し、月経が来るのを待って新しいシートで服用を再開します。またその周期は他の避妊法を使用する必要があります。
月経のような消退出血が来ない場合
消退出血が来なくても、通常通り次の周期も服用を続けます。2周期続けて消退出血が来ない場合や正しい方法で内服せず消退出血が来ない際は、妊娠の可能性も考えられるため医師の診察が必要になります。
下痢や嘔吐が続く場合
激しい下痢や嘔吐が続く場合は、低用量ピルが十分に吸収されない可能性があります。避妊効果に影響を及ぼすため、他の避妊法を併用し医師に相談してください。
低用量ピルを服用できない方・注意が必要な方
・以前経口避妊薬を使用して過敏症の既往がある方
・原因不明の性器出血のある方
・妊娠中または妊娠の可能性がある、産後4週間以内の方
・授乳中の方
・35歳以上で1日15本以上たばこを吸う方
・肥満の方
・以下の疾患又は既往のある方
深部静脈血栓症、肺塞栓症、抗リン脂質抗体症候群、血栓性素因、脳血管障害、片頭痛、心疾患、腎疾患、肝疾患、高血圧、糖尿病、子宮頸がん、子宮体がん、乳がん、ポルフィリン症、てんかん、テタニー、クローン病、
・4週間以内に手術を予定している、手術後2週間以内、長期間安静状態の方
・骨成長が終了していない方
・オムビタスビル水和物、パリタプレビル水和物、リトナビル配合剤を服用中の方
低用量ピルの副作用

副作用のほとんどは服用初期にみられ徐々におさまります
低用量ピルを服用してからおこる主な副作用(マイナートラブル)は、個人差はありますが、3か月以内に徐々に落ち着くことがほとんどです。
・不正出血
・吐き気
・胸のはり
・頭痛
など
ピルの種類を変えることで症状がおさまることもあります。ご自身に合ったピルをみつけるためにも、まずは内服を続け、症状が改善しないときは医師に相談しましょう。
血栓症のリスクについて
低用量ピルで注意しなければいけない副作用が、血液が固まって血管を塞いでしまう血栓症です。例えば肺の血管に血栓ができた場合は“肺塞栓症”、脳の血管に血栓ができた場合は“脳梗塞”と呼ばれます。
血栓症を疑う症状として、以下の“ACHES”が使われています。
これらの症状が出た場合には、速やかな検査や処置が必要な場合がありますので近隣の病院を受診してください。
A(Abdominal pain)強い腹痛
C(Chest pain)強い胸痛、息苦しさ、押しつぶされるような痛み
H(Headache)激しい頭痛
E(Eye/Speech problems)見えにくいところがある、視野が狭い、舌のもつれ、失神、けいれん
S(Severe leg pain)ふくらはぎの痛み・むくみ、握ると痛い、皮膚の赤み
1年間で1万人あたりの静脈血栓症の発症率は、低用量ピルを服用しない人の場合1~5人ですが、低用量ピルを服用すると3~9人に上昇するという報告があります。
一方で、妊娠中の静脈血栓症の割合は1年間で1万人あたり5~20人、また分娩後12週間の場合は、40~65人といわれています。
このことから、妊娠中~出産後の女性に比べると低用量ピルの内服による血栓症のリスクはかなり低いことがわかります。
低用量ピルは正しい知識をもって内服することで、心配しすぎる必要はなく、デメリットよりもはるかにメリットの多い薬であるといえます。
Loading now..
